蔵書情報
この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。
書誌情報
| 書名 |
わたしと日産 巨大自動車産業の光と影
|
| 著者名 |
西川 廣人/著
|
| 出版者 |
講談社
|
| 出版年月 |
2024.5 |
この資料に対する操作
電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。
資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
|
| 1 |
中央図書館 | 0181334749 | 537/サ/ | 1階図書室 | 49A | 一般図書 | 一般貸出 | 貸出中 | |
× |
| 2 |
はちけん | 7410352343 | 537/ニ/ | 図書室 | | 一般図書 | 一般貸出 | 貸出中 | |
× |
関連資料
この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。
 日韓の未来図 : 文化への熱狂と外…
日韓の未来図 : 文化への熱狂と外…
小針 進/著,大…
 北朝鮮拉致問題の解決 : 膠着を破…
北朝鮮拉致問題の解決 : 膠着を破…
和田 春樹/編,…
 Japan,Korea,and t…
Japan,Korea,and t…
Daniel R…
 ひろがる「日韓」のモヤモヤとわたし…
ひろがる「日韓」のモヤモヤとわたし…
加藤 圭木/監修…
 日朝交渉30年史
日朝交渉30年史
和田 春樹/著
 韓国の変化日本の選択 : 外交官が…
韓国の変化日本の選択 : 外交官が…
道上 尚史/著
 <ポスト帝国>の東アジア : 言説…
<ポスト帝国>の東アジア : 言説…
玄 武岩/著
 誤解しないための日韓関係講義
誤解しないための日韓関係講義
木村 幹/著
 北朝鮮外交回顧録
北朝鮮外交回顧録
山本 栄二/著
 韓国はどこに消えた!? : 世界か…
韓国はどこに消えた!? : 世界か…
高山 正之/著,…
 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
加藤 圭木/監修…
 日韓関係史
日韓関係史
木宮 正史/著
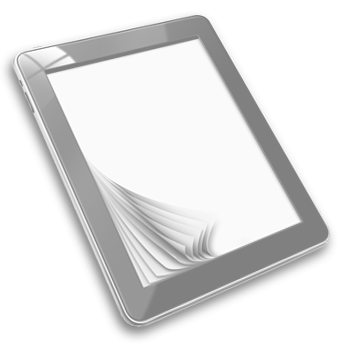 新たな時代の<日韓連帯>市民運動
新たな時代の<日韓連帯>市民運動
玄 武岩/編著,…
 新たな時代の<日韓連帯>市民運動
新たな時代の<日韓連帯>市民運動
玄 武岩/編著,…
 韓国問題の新常識
韓国問題の新常識
武藤 正敏/[ほ…
 日本VS韓国 : 対立がなくならな…
日本VS韓国 : 対立がなくならな…
池上 彰/著,「…
 歴史認識はどう語られてきたか
歴史認識はどう語られてきたか
木村 幹/著
 平成時代の日韓関係 : 楽観から悲…
平成時代の日韓関係 : 楽観から悲…
木村 幹/編著,…
 日韓の歴史問題をどう読み解くか :…
日韓の歴史問題をどう読み解くか :…
内海 愛子/[ほ…
 朝鮮半島と日本の未来
朝鮮半島と日本の未来
姜 尚中/著
 街場の日韓論
街場の日韓論
内田 樹/編,平…
 慰安婦
慰安婦
小林 よしのり/…
 日韓基本条約
日韓基本条約
内藤 陽介/著
 韓国併合110年後の真実 : 条約…
韓国併合110年後の真実 : 条約…
和田 春樹/著
 モンスターと化した韓国の奈落 : …
モンスターと化した韓国の奈落 : …
古森 義久/著
 韓国、ウソの代償 : 沈みゆく隣人…
韓国、ウソの代償 : 沈みゆく隣人…
高橋 洋一/著
 韓国とメディアは恥ずかしげもなく噓…
韓国とメディアは恥ずかしげもなく噓…
高山 正之/著
 ルポ「断絶」の日韓 : なぜここま…
ルポ「断絶」の日韓 : なぜここま…
牧野 愛博/著
 日韓の断層
日韓の断層
峯岸 博/著
 ドキュメント朝鮮で見た<日本> :…
ドキュメント朝鮮で見た<日本> :…
伊藤 孝司/著
 韓国への絶縁状
韓国への絶縁状
高山 正之/著
 統一朝鮮が日本に襲いかかる
統一朝鮮が日本に襲いかかる
豊田 有恒/[著…
 歴史を捏造する反日国家・韓国
歴史を捏造する反日国家・韓国
西岡 力/著
 それでも、私はあきらめない
それでも、私はあきらめない
黒田 福美/著
 竹島問題の起原 : 戦後日韓海洋紛…
竹島問題の起原 : 戦後日韓海洋紛…
藤井 賢二/著
 暴走する北朝鮮 : 緊迫する日米安…
暴走する北朝鮮 : 緊迫する日米安…
朝倉 秀雄/著
 「地政心理」で語る半島と列島
「地政心理」で語る半島と列島
ロー ダニエル/…
 ゆすり、たかりの国家 : 北朝鮮 …
ゆすり、たかりの国家 : 北朝鮮 …
西岡 力/著
 米朝戦争をふせぐ : 平和国家日本…
米朝戦争をふせぐ : 平和国家日本…
和田 春樹/著
 言いがかり国家「韓国」を黙らせる本
言いがかり国家「韓国」を黙らせる本
宮越 秀雄/著
 隣国への足跡 : ソウル在住35年…
隣国への足跡 : ソウル在住35年…
黒田 勝弘/著
 だまされないための「韓国」 : あ…
だまされないための「韓国」 : あ…
浅羽 祐樹/著,…
 在日の涙 : 間違いだらけの日韓関…
在日の涙 : 間違いだらけの日韓関…
辺 真一/著
 えん罪・欧州拉致 : よど号グルー…
えん罪・欧州拉致 : よど号グルー…
「えん罪・欧州拉…
 日韓友好の罪人たち : 学問的試論…
日韓友好の罪人たち : 学問的試論…
重村 智計/著
 喧嘩上等! : 反日国家の中心で反…
喧嘩上等! : 反日国家の中心で反…
竹嶋 渉/著
 嫌韓問題の解き方 : ステレオタイ…
嫌韓問題の解き方 : ステレオタイ…
小倉 紀蔵/著,…
 「反日」と「嫌韓」の同時代史 : …
「反日」と「嫌韓」の同時代史 : …
玄 武岩/著
 日韓<歴史対立>と<歴史対話> :…
日韓<歴史対立>と<歴史対話> :…
鄭 在貞/著,坂…
 柔らかな海峡 : 日本・韓国和解へ…
柔らかな海峡 : 日本・韓国和解へ…
金 惠京/著
前へ
次へ
日本-対外関係-韓国 日本-対外関係-朝鮮(北)
 日韓の未来図 : 文化への熱狂と外…
日韓の未来図 : 文化への熱狂と外…
小針 進/著,大…
 北朝鮮拉致問題の解決 : 膠着を破…
北朝鮮拉致問題の解決 : 膠着を破…
和田 春樹/編,…
 Japan,Korea,and t…
Japan,Korea,and t…
Daniel R…
 ひろがる「日韓」のモヤモヤとわたし…
ひろがる「日韓」のモヤモヤとわたし…
加藤 圭木/監修…
 日朝交渉30年史
日朝交渉30年史
和田 春樹/著
 韓国の変化日本の選択 : 外交官が…
韓国の変化日本の選択 : 外交官が…
道上 尚史/著
 そっか、日本と韓国って、そういう国…
そっか、日本と韓国って、そういう国…
ムーギー・キム/…
 <ポスト帝国>の東アジア : 言説…
<ポスト帝国>の東アジア : 言説…
玄 武岩/著
 誤解しないための日韓関係講義
誤解しないための日韓関係講義
木村 幹/著
 北朝鮮外交回顧録
北朝鮮外交回顧録
山本 栄二/著
 韓国愛憎 : 激変する隣国と私の3…
韓国愛憎 : 激変する隣国と私の3…
木村 幹/著
 韓国はどこに消えた!? : 世界か…
韓国はどこに消えた!? : 世界か…
高山 正之/著,…
 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
加藤 圭木/監修…
 絶望の文在寅、孤独の金正恩 : 「…
絶望の文在寅、孤独の金正恩 : 「…
重村 智計/著
 日韓関係史
日韓関係史
木宮 正史/著
 この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体
この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体
青木 理/[著]…
 捏造メディアが報じない真実 : 習…
捏造メディアが報じない真実 : 習…
大高 未貴/著
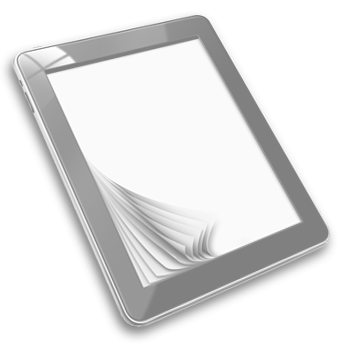 新たな時代の<日韓連帯>市民運動
新たな時代の<日韓連帯>市民運動
玄 武岩/編著,…
 新たな時代の<日韓連帯>市民運動
新たな時代の<日韓連帯>市民運動
玄 武岩/編著,…
 韓国問題の新常識
韓国問題の新常識
武藤 正敏/[ほ…
 日本VS韓国 : 対立がなくならな…
日本VS韓国 : 対立がなくならな…
池上 彰/著,「…
 歴史認識はどう語られてきたか
歴史認識はどう語られてきたか
木村 幹/著
 平成時代の日韓関係 : 楽観から悲…
平成時代の日韓関係 : 楽観から悲…
木村 幹/編著,…
 日韓の歴史問題をどう読み解くか :…
日韓の歴史問題をどう読み解くか :…
内海 愛子/[ほ…
 朝鮮半島と日本の未来
朝鮮半島と日本の未来
姜 尚中/著
 街場の日韓論
街場の日韓論
内田 樹/編,平…
 慰安婦
慰安婦
小林 よしのり/…
 日韓基本条約
日韓基本条約
内藤 陽介/著
 モンスターと化した韓国の奈落 : …
モンスターと化した韓国の奈落 : …
古森 義久/著
 韓国経済はクラッシュする : 文在…
韓国経済はクラッシュする : 文在…
室谷 克実/著,…
 韓国、ウソの代償 : 沈みゆく隣人…
韓国、ウソの代償 : 沈みゆく隣人…
高橋 洋一/著
 韓国とメディアは恥ずかしげもなく噓…
韓国とメディアは恥ずかしげもなく噓…
高山 正之/著
 ルポ「断絶」の日韓 : なぜここま…
ルポ「断絶」の日韓 : なぜここま…
牧野 愛博/著
 日韓の断層
日韓の断層
峯岸 博/著
 ドキュメント朝鮮で見た<日本> :…
ドキュメント朝鮮で見た<日本> :…
伊藤 孝司/著
 韓国への絶縁状
韓国への絶縁状
高山 正之/著
 統一朝鮮が日本に襲いかかる
統一朝鮮が日本に襲いかかる
豊田 有恒/[著…
 歴史を捏造する反日国家・韓国
歴史を捏造する反日国家・韓国
西岡 力/著
 決定版・慰安婦の真実 : 戦場ジャ…
決定版・慰安婦の真実 : 戦場ジャ…
マイケル・ヨン/…
 それでも、私はあきらめない
それでも、私はあきらめない
黒田 福美/著
 感情的になる前に知らないと恥ずかし…
感情的になる前に知らないと恥ずかし…
富坂 聰/著
 竹島問題の起原 : 戦後日韓海洋紛…
竹島問題の起原 : 戦後日韓海洋紛…
藤井 賢二/著
 「北朝鮮の脅威」のカラクリ : 変…
「北朝鮮の脅威」のカラクリ : 変…
半田 滋/著
 米軍の北朝鮮爆撃は6月! : 米、…
米軍の北朝鮮爆撃は6月! : 米、…
副島 隆彦/著
 中華思想を妄信する中国人と韓国人の…
中華思想を妄信する中国人と韓国人の…
ケント・ギルバー…
 中韓がむさぼり続ける「反日」という…
中韓がむさぼり続ける「反日」という…
ケント・ギルバー…
 暴走する北朝鮮 : 緊迫する日米安…
暴走する北朝鮮 : 緊迫する日米安…
朝倉 秀雄/著
 「地政心理」で語る半島と列島
「地政心理」で語る半島と列島
ロー ダニエル/…
 ゆすり、たかりの国家 : 北朝鮮 …
ゆすり、たかりの国家 : 北朝鮮 …
西岡 力/著
 米朝戦争をふせぐ : 平和国家日本…
米朝戦争をふせぐ : 平和国家日本…
和田 春樹/著
前へ
次へ
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1008001858415 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
わたしと日産 巨大自動車産業の光と影 |
| 書名ヨミ |
ワタシ ト ニッサン |
| 著者名 |
西川 廣人/著
|
| 著者名ヨミ |
サイカワ ヒロト |
| 出版者 |
講談社
|
| 出版年月 |
2024.5 |
| ページ数 |
255p |
| 大きさ |
20cm |
| 分類記号 |
537.067
|
| 分類記号 |
537.067
|
| ISBN |
4-06-536059-0 |
| 内容紹介 |
高度成長、バブル、経営危機、V字回復、そしてゴーン逮捕-。ゴーン会長のもと、日産社長を務めた男はそのとき何を考えていたのか? 日本人サラリーマンが目撃した巨大自動車産業「もうひとつの戦後史」。 |
| 著者紹介 |
東京大学経済学部卒業。株式会社アイディーエス顧問。元日産自動車取締役。 |
| 件名 |
日産自動車 |
| 個人件名 |
西川 廣人 |
| 言語区分 |
日本語 |
| (他の紹介)内容紹介 |
近年、インターネットなどで排外主義・人種主義が拡がっている。それは、日韓関係や在日朝鮮人をめぐる「嫌韓」意識として表れている。このような“嫌韓流”現象を多角的・批判的に分析するとともに、日本人とコリアンが新しい関係をつくるための手がかりとなる“思考の糧”と“歴史の見方”を提供する。「“嫌韓流”の解剖ツール」「マンガ表現から見た“嫌韓流”」「植民地支配は朝鮮を豊かにしたか」「朝鮮人強制連行はなかったのか」「参政権は「国民固有の権利」か」「在日コリアンに対する差別はなくなったのか」「韓国の「過去清算」はどうなっているか」「過去に向き合うことは「自虐史観」か」等20章。 |
| (他の紹介)目次 |
第1部 “嫌韓流”現象を読み解く(“嫌韓流”の解剖ツール
マンガ表現から見た“嫌韓流”―キャラクター操作を通じてのレイシズム)
第2部 日本の朝鮮植民地支配をめぐって(韓国併合は朝鮮人が望んだものか
植民地支配は朝鮮を豊かにしたか
日本人と朝鮮人は平等だったか
日本人はハングルを広めたか
創氏改名とは何だったのか
朝鮮人強制連行はなかったのか
「慰安婦」制度は犯罪ではなかったのか)
第3部 在日コリアンと日本社会(朝鮮人は戦前、どのように来日し、生活してきたか
「解放された」在日朝鮮人は戦後をどう迎えたのか
参政権は「国民固有の権利」か
他民族共生社会のなかで民族学校をどう考えたらよいか
在日コリアンに対する差別はなくなったのか)
第4部 戦後の日韓関係について(戦後の日韓関係をどのように考えたらよいのか
日韓条約で植民地支配は清算されたか
竹島問題はどう考えたらよいか
韓国の「過去清算」はどうなっているのか
韓国は「反日」一色なのか
過去に向き合うことは「自虐史観」か) |
| (他の紹介)著者紹介 |
田中 宏
1937年生れ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。龍谷大学経済学部教授。専攻は日本アジア関係史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
板垣 竜太
1972年生れ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。同志社大学社会学部社会学科専任講師。専攻は朝鮮近現代社会史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
内容細目表
前のページへ